フォルクローレの曲
以前資料室に掲載していた曲の解説は間違いも多かったので、改めて調べなおして掲載していきます。 少しずつ増やしていくつもりですが、年に数曲が限度だと思います。思った以上に大変な作業でした。 [コンドルは飛んで行く] [レーニョ・ベルデ] [サンフランシスコへの道] [プル・ルーナス] [エル・ミネロ] [母の叫び] [アンデスの祭り] [コモ・ア・セチョ] [夢想花]- コンドルは飛んで行く EL CONDOR PASA/Daniel Alomia Robles
- あまりに有名で、曲の由来についての研究も進んでいる。参考サイトを見ればほとんどのことは書かれているので、それらを基にして自分なりにまとめてみた。
現在最もよく耳にする構成は、イントロダクションに続いてヤラビのリズムの部分とワイノのリズムの部分からなる2部構成である。ヤラビとワイノの間にフォックス・インカイコ(トロットあるいはパサカージェとも)のリズムの部分を入れた3部構成で演奏されることもある。ヤラビとフォックス・インカイコはテンポは違うがメロディラインはほとんど同じである。
1913年にペルー人作曲家であり民俗音楽研究家であったダニエル・アロミア=ロブレス(Daniel Alomía Robles,1871-1942)が、自身で採譜した伝承曲のメロディをモチーフにして書いたSoy la paloma que el nido perdidoというタイトルのサルスエラ(オペラの一種)の序曲として発表。その段階ではヤラビ部分は存在しなかった。このサルスエラはペルーの先住民労働者と鉱山を所有する植民者との間の対立を描いた物語で、アンデスの大空をコンドルが飛んでいるシーンに演奏された。台本を書いたのはリマの劇作家のJulio de La Paz(Julio Baudouinの仮名)で、まれに「コンドルは飛んで行く」の作詞者と評されることがあるが、それは誤りである。また、「インカ帝国の王女を主人公にしたサルスエラ」と説明しているサイトもかなりの数見られるが、これも誤りである。かくいう私も以前そのように書いていた。当時はネットでの情報は少なく、書籍かアルバムの解説に書かれていたのを引用したと記憶しているが、その出典はいまではわからなくなってしまった。
現存するもっとも古い録音。1917年。
 El Cóndor Pasa .1917. Primera Grabación.Orquesta del Zoológico
El Cóndor Pasa .1917. Primera Grabación.Orquesta del Zoológico
コンドル誕生100年を記念して原曲を再現した演奏
 El Cóndor Pasa Única Versión Original, según la partitura de Daniel Alomía Robles
El Cóndor Pasa Única Versión Original, según la partitura de Daniel Alomía Robles
次に、下の動画は1937年の録音のもの。Orquesta tipica Bolivianaというボリビアのオーケストラの演奏で録音はアルゼンチンで行われ、チリでプレスされたペルーの曲とややこしいのだけど、だいたい同じような演奏になっている。唐突にフォックスインカイコが始まるので逆に変な感じに聞こえるが元来このようなものであったのだろう。
 El cóndor pasa...1937.Grabación Boliviana. Felipe V. Rivera y su Orquesta Típica Boliviana.
El cóndor pasa...1937.Grabación Boliviana. Felipe V. Rivera y su Orquesta Típica Boliviana.
ではいつからスローテンポのヤラビになったのか。その初出はアメリカのEdward B. Marks Music Corpに登録されている、作者自身の編曲とされるピアノ譜に求められる。その譜面を実際に演奏した動画がこちらである。
 Piano Peruano.1933 "El cóndor pasa..." Versión Original de Daniel Alomía Robles.
Piano Peruano.1933 "El cóndor pasa..." Versión Original de Daniel Alomía Robles.
この演奏では、ヤラビのあとワイノになっており、フォックス・インカイコが存在しない。つまり当初はあくまで2部構成であり、もともとフォックス・インカイコのリズムのパートをヤラビのリズムに変化させたものであったと考えられる。
1955年に発売されたエドゥアルド・ファルーのギター演奏もこの流れを汲んだものである(T.K.-LD-55-031,Argentina,1955)。ここで一つ原曲との大きな違いとしてあげられるのは、ダニエルのヤラビはミラソ#ラシドシドレミー ソーミー レドラーであるが、ファルーのギター演奏は同じ調で表すとミラソ#ラシドシドレミーソーミー ソーミー レドラー シドラーと少し長尺になっている。以後のグループはこのどちらかに系統が分けられる。
 El condor pasa · Eduardo Falu
El condor pasa · Eduardo Falu
ファルーの録音とほぼ同時期にエクアドルのグループLos Incaicosの演奏でアルバムCancionero Incaico-The Music Of Bolivia, Ecuador & Peru - Volume 1 (1956年、US,SMC-518)が発売される。この中で「コンドルは飛んで行く」が弦楽器で演奏されている(AYLLU ASTUR2019年10月13日の記事)。このレコードには歌詞カードが付いているが、「コンドルは飛んで行く」は「sin palabras(歌詞なし)」と書かれている。 なお、このLos Incaicosのアルバムは1954年に京都でレコード鑑賞会が行われたとされているので(ラテン・フォルクローレ・タンゴ』および雑誌『中南米音楽'75別冊フォルクローレのすべて』の永田文夫氏の言。小林智詠氏のご教示による。)、アメリカ盤以前にアルゼンチン盤などが先行して販売されていた可能性がある。もしそうならファルーの録音以前の音源ということになるが不詳。
フォルクローレの楽器で演奏されたのは1958年のACHALAYというグループのアルバムが初源と言われている。ヤラビ+ワイニョの2部構成である。ACHALAYはLOS INCASの初期メンバーのチャランゴ奏者のリカルド・ガレアッツィ(Ricardo Galeazzi)が1957、58年ごろに結成したグループである。リカルド・ガレアッツィは、上述のLos Incaicosのアルバムを聴いてそれに触発されてケーナやチャランゴ、ギターで演奏するアレンジをしたという(AYLLU ASTURによる)。
 Conjunto Sol Del Peru – El Condor Pasaリンク切れ予備動画
Conjunto Sol Del Peru – El Condor Pasaリンク切れ予備動画
 El Condor Pasa
El Condor Pasa
ここまではヤラビかフォックス・インカイコかというリズムの違いはあっても、すべて2部構成で演奏されている。それでは3部構成になったのはいつからだろうか。
3部構成の原点は探せなかったが、見つかった中で古いのは1961年のConjunto Sol Del Peruの録音で、現在とほぼ同じ3部構成になっている。これ以前のものがあったらご教示願いたい。
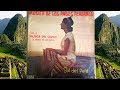 Conjunto Sol Del Peru – El Condor Pasa
Conjunto Sol Del Peru – El Condor Pasa
1963年にロス・インカスがこの曲を録音したアルバムを発表する。この時のロス・インカスの演奏はイントロのあとヤラビを2回繰り返してワイノになる2部構成であった。またこの際、リーダーのホルヘ・ミルチベルグ(Jorge Milchberg,1928-2022)がEl Incaの名で自作曲としてアルゼンチンの著作権協会に登録したことであたかも彼が作曲したと勘違いされてしまう。

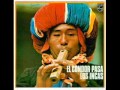
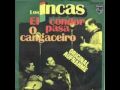
 1965年3月23日フランスでの3人の演奏
1965年3月23日フランスでの3人の演奏
1966年ボリビアのロス・ハイラスの演奏もロス・インカスと同じ2部構成となっている。
 LOS JAIRAS - CONDOR PASA (Disco completo)
LOS JAIRAS - CONDOR PASA (Disco completo)
しかしほぼ同時期のErnestoとLuchoのCavour兄弟の演奏(CAMPO WAO-007)では中間部をチャランゴとケーナで掛け合いする3部構成である。このように、ロス・インカスと前後して2部構成と3部構成は両方とも演奏されていたことがわかる。この時点で現在演奏されているスタイルの要素がすべて出そろったと言って良い。
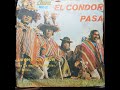 LUCHO CAVOUR - EL CONDOR PASA (EP)
LUCHO CAVOUR - EL CONDOR PASA (EP)
この曲が世界的に有名になり、日本人の耳にはいるようになったのはサイモン&ガーファンクルによってカバーされたことによる。
1965年、ポール・サイモンがパリの劇場で公演していたロス・インカスの演奏を聴き、この曲を気に入り、英語の歌詞をつけて1970年にロス・インカスの演奏で録音し、世界的にヒットする。こちらのバージョンではヤラビの部分のみで、フォックス・インカイコとワイノ部分は省略された。
サイモン&ガーファンクルのヒットののち、1970年代後半にダニエル・アロミア=ロブレスの息子で、映画監督として著名なアルマンド・ロブレス・ゴドイ(Armando Robles Godoy,1923-2010)がポール・サイモンに対して著作権訴訟を起こし、著作権は本来の作者に帰することになった。
その後「コンドルは飛んで行く」は、ファシオ・サンティジャン、アントニオ・パントーハ、ウニャ・ラモス、レーモン・テブノーといった世界的に有名なケーナ奏者によって演奏され、世界中に羽ばたいて行った。
ここで少し話が横道にそれるが、今回いろいろなサイトを調べている過程でこの曲が惑星探査機ボイジャーに搭載されたゴールデンレコードの中に収録されていると書かれたサイトをいくつか見ることがあった。日本のウィキペディアのボイジャーのゴールデンレコードの項目や、海外のサイトでも見られた。
Wikipediaボイジャーのゴールデンレコード
Musica Andina-El Condor Pasa
このことは私にとって初耳で、もしそうなら今までに聞いたことがあるはずだと思って、詳しく調べてみたら、その記載は誤りであると判明した。コンドルは飛んでいくと書かれている箇所は実際にはMusicians from Ancash - Roncadoras and Drumsというタイトルの演奏が収録されている。このリンクの17曲目である。
Voyager Golden Record
なぜこのような間違いが起こったのか不明である。もしかしたら当初は「El Condor Pasa」をゴールデンレコードに収録する予定だったのが、最終的に差し変わってしまったとか、ありそうな話であるがあくまでも憶測にすぎない。とにもかくにもネット上にはしれっと嘘が混ざっているから恐ろしい。今までの記述もネット上の記事を参考にしているのだけど、間違いがあるかもしれないので鵜呑みにはしないでもらいたい。
コンドルは飛んで行くの歌詞について
アロミア=ロブレスの作曲したバージョンでは歌詞がついていなかったと考えられる。コンドル誕生100年を記念して復元されたサルスエラの最後にこの曲が演奏されている。
 El Cóndor Pasa...Zarzuela Completa...Daniel Alomía Robles.
El Cóndor Pasa...Zarzuela Completa...Daniel Alomía Robles.
1970年にサイモン&ガーファンクルが英語の歌詞をつけるが、それは翻訳でなく独自の解釈の歌詞である。ダニエルの息子のアルマンド・ロブレスは著作権訴訟後にサイモン&ガーファンクルの英語の歌詞をスペイン語に翻訳して発表するもあまり普及しなかったようだ。期待はずれのものであったからであろう。ちなみにダニエルには12人の子供がいたらしい。最初の妻との間に10人の子供が、後妻との間に2人の子供がいて、アルマンドは後者になる。
アルマンド・ロブレスの作詞したコンドルは飛んで行く。
Prefiero ser un cóndor que un gorrión
y volar sin soñar y sin canción.
Prefiero ser un árbol que una flor
y crecer sin temer y sin dolor.
Buscar sin encontrar jamás
sin descansar sin fe ni paz.
Partir y nunca regresar y así vivir
y así pasar. Y así pasar.
Prefiero ser el beso que el amor
y olvidar sin llorar y sin rencor.
Prefiero ser la lluvia sobre el mar
y morir sin sufrir y sin cesar.
Buscar sin regresar jamás
sin encontrar sin fe ni paz.
Partir y nunca descansar y así vivir
y así pasar. Y así pasar…
サイモン&ガーファンクルの歌詞が「カタツムリよりも雀になりたい」「釘よりもハンマーになりたい」というのに対し、アルマンドの歌詞は「スズメよりもコンドルになりたい」「花より木になりたい」というように、単純な翻訳でなくむしろ翻案といった方が良いだろう。ただし自由を求めるという内容のコンセプトは同じようなものであった。
サイモン&ガーファンクルのヒットにより、その後この曲を演奏や歌を収録したアルバムが爆発的に増える。 スペイン語の歌詞もたくさん作られている。 私は世代的にクリスティーナとウーゴの歌によって有名になったスペイン語歌詞が気に入っている。歌詞は同じアルゼンチンのグループ、Los Cantores de Quilla HuasiのOscal Vallesの作詞である。
 EL CONDOR PASA CRISTINA Y HUGO
EL CONDOR PASA CRISTINA Y HUGO
 Los Cantores de Quilla Huasi(1972)
Los Cantores de Quilla Huasi(1972)
En el imperio incaico el indio está,sin luz, sólo está,triste está.
Detrás de los silencios quedará jamás, nunca más, volverá.
El inca ya se fué,a morir rumbo al sol,y en su alma un condor va a llorar su dolor volando
Vuela, vuela el cóndor la inmensidad, sombra de la altipampa.
Sueño de la raza americana sangre de la raza indiana
El inca há sido traicionado,llorando las quenas están.
La Pachamama al coya enseño a morir por la libertada!
Plácido Domingoの歌詞のバージョンもよく耳にする。
 EL CÓNDOR PASA (letra e vídeo) com PLÁCIDO DOMINGO, vídeo MOACIR SILVEIRA
EL CÓNDOR PASA (letra e vídeo) com PLÁCIDO DOMINGO, vídeo MOACIR SILVEIRA
El condor de los andes desperto
con la luz de un feliz amaneser.
Sus alas lentamente despego
y bajo al rio azul para beber.
Tras el la tierra se cubrio
de verdos, de amor, y paz
tras el el prado floresio y el sol broto en el trigal.
El condor al pasar me dijo a mi
sigeme mas aya y tu veras.
En la espalda del condor me sente
y a volar cada vez mas el cielo alcansar.
Mirar mirar hacia la tierra
tan distinto de lo que vi
fronteras no se pueden ver
todo el mundo desde hay
es lo que vi.
El condor de los andes desendio
al llegar un feliz amaneser.
El condor al igual se desperto
repitio su sobre l rebaño
todos iguales.
Tras el la tierra se cubrio
de verdor, de amor y paz
tras el el prado floresio y el sol broto en el trigal
en el trigal.
Los Fronterizosの歌詞
 El Condor Pasa (Interpretado por Los Fronterizos)
El Condor Pasa (Interpretado por Los Fronterizos)
El cóndor pasa el cielo del Perú
del sol, hijo es, del Perú Inca
volando por sobre los Andes va
como un guardián, del pueblo indio.
no hay conquistador capaz
de doblar tu valor
inca, eres hijo del sol
de Atahualpa el valor
hijo sos del Dios Inca.
Pronto yo vuelva a mi tierra
me acompañara el dolor
de aquellos hermanos míos
que sacrificaron su valor.
vuelve, vuelve, vuelve pronto
de adonde fuiste cóndor
vuelve ya por tus guerreros
llévame a luchar junto con vos.
Inca, eres hijo del sol
de Atahualpa el valor
Hijo sos, del Dios Inca
de América india fuiste señor
honor, Impetu, al pueblo indio.
El cóndor pasa el cielo del Perú (del Perú)
del sol (hijo es), del Perú
Inca.
LOS TUCU TUCU(1972)の歌詞もまた違うものである。歌詞は省略する。
 Los Tucu Tucu - El Cóndor Pasa
Los Tucu Tucu - El Cóndor Pasa
ケチュア語バージョン。
 EL CÓNDOR PASA (QUECHUA)
EL CÓNDOR PASA (QUECHUA)
 EL CÓNDOR PASA (QUECHUA)
EL CÓNDOR PASA (QUECHUA)
Yaw kuntur llaqtay urqupi tiyaq
maymantam qawamuwachkanki,
kuntur, kuntur
apallaway llaqtanchikman, wasinchikman
chay chiri urqupi, kutiytam munani,
kuntur, kuntur.
Qusqu llaqtapim plazachallanpim
suyaykamullaway,
Machu Piqchupi Wayna Piqchupi
purikunanchikpaq.
訳
アンデスの雄大なコンドルよ。私を我が家に連れて行っておくれ。
愛する土地に帰って、インカの兄弟たちと暮らしたい。
クスコのメイン広場で私を待っていてください。
マチュピチュとワイナピチュに散歩に行きましょう。
以下はYoutubeにあった「コンドルは飛んで行くの歴史」をつづった動画である。スペイン語だけど、上記の知識があればだいたいの内容は伝わるだろう。なお(1)の動画の1'20"以降ではIma Sumacが1960年にヤラビの部分を歌っているシーンが映されている。映像はたしかに1960年ロシア公演のものだが、流れている曲は1971年の録音を重ねたものである。実際の音声は「→こちら」で別の曲を歌っているので注意が必要だ。これに気が付いた時、思わず「孔明の罠か!巧妙すぎるだろ。」と叫んでしまった。20年前と比べてインターネットでこれだけのことが調べられるようになったが、中には間違った情報もあるので、何度も言うようだけど、すべて鵜呑みにしない方がよい。
 (1)La Historia del Condor Pasa
(1)La Historia del Condor Pasa
 (2)Daniel Alomía Robles y el Cóndor Pasa, Historia Peruana
(2)Daniel Alomía Robles y el Cóndor Pasa, Historia Peruana
 (3)Historia detrás del Cóndor Pasa
(3)Historia detrás del Cóndor Pasa
- 参考サイト
- レーニョ・ベルデ LEÑO VERDE/Ernesto Cavour
- エルネスト・カブール(1940-2022)の傑作。初出は1975年のアルバムCHARANGO Y CONJUNTO Vol.2。サンポーニャを吹いているのはラミロ・カルデロン(Ramiro Calderon)。カブールがレコーディングをしていて、アルバムとして曲数がたりないということがわかり、その場で即興で作曲したという逸話を耳にしたことがあるが、このことを福田大治氏に確認をしたところ、そのような話はカブールさんから聞いたことはないとのことであった。福田氏は別の逸話を話してくれた。それは、もともとはケーナの曲として作ったものが、録音の日ケーナ奏者が酔っぱらってこなかったために代わりにサンポーニャで吹いたというもの。でもこれもボリビアっぽい冗談であって事実でないらしい。即興で作ったとは思えず、時間をかけて念入りに緻密に計算されて作られたものとのことだった。「緑の大木」という邦題が広まっているが、これは1979年にポリドール社から発売された初来日の記念盤「CANTO DEL VIENTO/風の詩」で書かれていたことに加え、曲のイメージとマッチしていたことから広く知られるようになったと思われる。しかしカブール本人に詳しく尋ねると、緑の木というのは、乾燥しきれずに水分を含んだ「生乾きの薪」のことらしい。福田大治氏はこの曲について直訳は「緑の薪」で、意訳すれば「青二才、または青二才の暴走」と述べている。さらに以前に本人から聞いた話として「レーニョleñoとは標準スペイン語ではレーニャleña(木から伐採された丸太"tronco"を、かまど用などにざっくり割った薪)のことで、男気を表すために男性形(-ño)の造語にしたそうです。」と記述している(Facebook2022年8月14日の投稿)。推測であるが、このタイトルに込められた意味は、「私たちはこのくらいの演奏では満足していない、まだまだもっとすごい演奏ができるんだぞ」という意気込みを表しているのではないかと思う。それまでケーナがメロディの主線になることが多かったが、この曲以降、サンポーニャがソロでメロディを吹くというスタイルが広まっていった。サンポーニャの地位向上のエポック・メイキング的な曲ともいえる。その後いろいろなグループが演奏しているのでいくつかおすすめの演奏を載せておく。
最初の録音(Ernesto Cavour,Lucho Cavour,Ramiro Calderon,Freddy Santos)
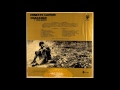 Leño verde - Ernesto Cavour
Grupo Naira(Ernesto Cavour,Lucho Cavour,Jhony Bernal,Luis Rico)の演奏
Leño verde - Ernesto Cavour
Grupo Naira(Ernesto Cavour,Lucho Cavour,Jhony Bernal,Luis Rico)の演奏
 Ernesto Cavour - Grupo-Naira - El Leno Verde ( Jhony"mono" Bernal )
Rumillajtaの演奏。1990年イギリス、エジンバラ・ライブより(Juan Jorge Laura,Adrian Villanueva,Nestor Tintaya,Juan Carlos Cordero,Miguel Angel Puña)。
Ernesto Cavour - Grupo-Naira - El Leno Verde ( Jhony"mono" Bernal )
Rumillajtaの演奏。1990年イギリス、エジンバラ・ライブより(Juan Jorge Laura,Adrian Villanueva,Nestor Tintaya,Juan Carlos Cordero,Miguel Angel Puña)。
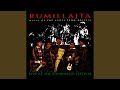 Leño Verde (En Vivo)
Perumantaの演奏。動画にはSAVIA ANDINAとあるが誤り(ここにもネットの落とし穴が)。アレンジが気に入っている。Perumantaの"Zamponas Y Charango Vol.1"に収録されている。このCDジャケット裏(←クリックで表示)
では1998年リリースとあるが、自分の知っている音源はカセットで1992年以前に聴いたもので、曲数もこれより少なく曲順もバラバラなので、復刻盤と思われる。元のアルバムはネット上では見つけられなかった。
Leño Verde (En Vivo)
Perumantaの演奏。動画にはSAVIA ANDINAとあるが誤り(ここにもネットの落とし穴が)。アレンジが気に入っている。Perumantaの"Zamponas Y Charango Vol.1"に収録されている。このCDジャケット裏(←クリックで表示)
では1998年リリースとあるが、自分の知っている音源はカセットで1992年以前に聴いたもので、曲数もこれより少なく曲順もバラバラなので、復刻盤と思われる。元のアルバムはネット上では見つけられなかった。
 PERUMANTA LEÑO VERDE
2009年9月23日東京・築地での演奏(エルネスト・カブール、福田大治、岡田浩安・敬称略)。
PERUMANTA LEÑO VERDE
2009年9月23日東京・築地での演奏(エルネスト・カブール、福田大治、岡田浩安・敬称略)。
 LEÑO VERDE ERNESTO CAVOUR (レーニョ・ベルデ エルネスト・カブール)
Savia Andina 2018年ベルギー、ブリュッセルでのコンサート。Oscar Santos Castro Canaviri、Juan Gerardo Arias Paz、José Edwin Herrera Jaen、David Edwin Pérez Ballesteros、Martin Arias de la Fuente。Edwin Herreraっていったん脱退していたよね?メンバーに復帰してたんだ。
LEÑO VERDE ERNESTO CAVOUR (レーニョ・ベルデ エルネスト・カブール)
Savia Andina 2018年ベルギー、ブリュッセルでのコンサート。Oscar Santos Castro Canaviri、Juan Gerardo Arias Paz、José Edwin Herrera Jaen、David Edwin Pérez Ballesteros、Martin Arias de la Fuente。Edwin Herreraっていったん脱退していたよね?メンバーに復帰してたんだ。
 Savia Andina Leño verde
サビア・アンディーナのアルバムでの初出は1980年Bolivia。最初に聴いた時はすごい衝撃を受けた。音源はこちら(Alcides Enrique Mejía Hany,
Eddy Navia Dalence,Gerardo Arias Paz,Oscar Castro Canaviri)
なんとこれをケーナで演奏!!菱本幸二と木下尊惇と安達満里子(敬称略)のトリオの演奏。コメントもあるのでFaceboookをリンクします。
最後に手前味噌ながら自分も参加しているYMSサクセションでの演奏から。YMSサクセション(2016年)(菅沼ユタカ、菅沼摂子、菅沼聖隆、石野雅彦)
Savia Andina Leño verde
サビア・アンディーナのアルバムでの初出は1980年Bolivia。最初に聴いた時はすごい衝撃を受けた。音源はこちら(Alcides Enrique Mejía Hany,
Eddy Navia Dalence,Gerardo Arias Paz,Oscar Castro Canaviri)
なんとこれをケーナで演奏!!菱本幸二と木下尊惇と安達満里子(敬称略)のトリオの演奏。コメントもあるのでFaceboookをリンクします。
最後に手前味噌ながら自分も参加しているYMSサクセションでの演奏から。YMSサクセション(2016年)(菅沼ユタカ、菅沼摂子、菅沼聖隆、石野雅彦)
- サンフランシスコへの道 CAMINO A SAN FRANCISCO/HUGO "CHICHIN" COIMBRA GUTIERREZ,JORGE BEILLIARD
- この曲はアルゼンチンの著作権協会SADAICに1969年に登録されており、現時点で私が確認できた一番古い録音は1971年にギタリストのFreddy Soloのアルバム "Mil Guitarras"に収められているものである。
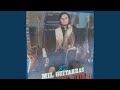 Camino a San Francisco
Camino a San Francisco
 Camino a San Francisco
Camino a San Francisco
1976年にロス・ライカスのデビューアルバム"IDOLOS DE QUENA"(VICTOR SWX-7130)に収録され、一躍有名になった。
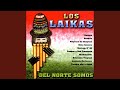 LOS LAIKAS
LOS LAIKAS
後年の録音では少しアレンジを変えておしゃれになっている。
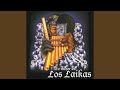 LOS LAIKAS
LOS LAIKAS
 LOS LAIKAS
LOS LAIKAS
BOLIVIA.COMの2002年10月15日の記事によると、ウーゴ・コインブラは1945年1月3日にボリビアのサンタクルス・デ・ラ・シエラの南にあるグティエレスの町で生まれ、その後12歳でアルゼンチンに移ったとのこと。この曲は作者が14歳の時に作曲したと書かれている。Renan VargasとOmar Ibarraと組んでLos Malbinosというトリオで活動していた。
以前見たyoutubeのコメントの本人の書き込みではサルタ市に住んでいるということが書かれていた。さらに本人のFacebookでは再びサンタクスル・デ・ラ・シエラに移ったことがわかる。14歳であればサルタ市に住んでいたときの作曲と考えられる。 この曲は長年の間「続・夕日のガンマン」のテーマソングと紹介されることが多かった。なぜかというとロス・ライカスのレコードの日本盤解説に本田健治氏が『サンフランシスコへの道 南米ではこうタイトルがついているが、これは映画「続・夕陽のガンマン」のテーマ曲。この映画がヒットしたせいもあっていろいろなアーティストが演奏するが(ケーナではあまり聞かないが)、ライカスのはたいへん元気で勇ましい演奏だ。』と書いてあるからだ(ケーナの寵児~ロス・ライカス,VICTOR,SWX-7130,1976年)。この文章が何かの資料をみて書かれたものか、メンバーから聞いたことを書いたのか不明であるが、「続・夕陽のガンマン」のテーマ曲は「LO BUENO,LO MALO Y LO FEO(善・悪・穢)」である。こちらもライカスは演奏している(1978/INTERNACIONAL )のでおそらくこの曲と混同したメンバーから聞いて書いたものではないかと思われる。メンバーが間違えてしまっているなら、本田健治氏には非がないのだろうけど、ひと手間かけて映画を確認していたら、これほど誤った解釈が浸透することはなかっただろう。勘違い説を裏付ける事例がもう一つある。ライカスのメンバーであり、ロス・トレス・アミーゴスとして日本で活動していたルイス・カルロス・セベリッチ氏にこの曲の出典を尋ねたら、彼はフランコ・ネロ主演のマカロニ・ウェスタン「ジャンゴ」のテーマソングだと答えた。ジャンゴは1966年製作で日本では「続・荒野の用心棒」という邦題で公開されている。また別の映画のタイトルが出てきたが、いずれにしてもこの曲は使われていない。ライカスのメンバーですら勘違いしているので、西部劇のテーマソングというのは間違いだろう。
勘違いした方の曲。続・夕陽のガンマンと続・荒野の用心棒も参考に挙げておく。
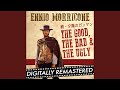 続・夕陽のガンマン - The Good, The Bad and The Ugly
続・夕陽のガンマン - The Good, The Bad and The Ugly
 01- Lo Bueno Lo Malo y Lo Feo - Los Laikas
01- Lo Bueno Lo Malo y Lo Feo - Los Laikas
 続・荒野の用心棒 Django (Main Titles SongOriginal Italian Stereo)
続・荒野の用心棒 Django (Main Titles SongOriginal Italian Stereo)
では、本来はどのような曲だったのか?Youtubeに作者自身が歌っている動画がいくつかあるので紹介する。
 MUJERES COMO VOS ENTREVISTA A HUGO CHICHIN COIMBRA EL ABOGADO CANTAUTOR
MUJERES COMO VOS ENTREVISTA A HUGO CHICHIN COIMBRA EL ABOGADO CANTAUTOR
Hugo Coimbraがこの曲についてインタビューをうけている貴重な動画である。私のスペイン語のヒアリング能力では細かいところまで聞き取れないので、間違いがあるといけないので、詳しく書けないが、曲のヒットの経緯が語られているようだ。ライカスについても触れられている。
この曲を収録したCDのジャケットでは若かりし頃の作者Hugo Coimbraのバックにゴールデンブリッジが映っていることから、サンフランシスコはカリフォルニア州のそれであると思われる。
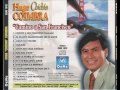
私はこのサンフランシスコは作者が少年期に育ったアルゼンチンのサルタ州付近の地名であるかと考えていた。以前資料室にこの曲の解説を掲載した際、サンフランシスコはアルゼンチン北部の小さな村とのことであると書いた。それはロス・ライカスのカルロス・フローレスがそのように言っていたということを伝え聞いたていたからなのだが、どうやらこれも間違いあるいは勘違いであると思われる。そもそも西部劇のテーマソングと勘違いしていた人が、サンフランシスコをアルゼンチンの地名だというのもおかしな話で、どこかで間違って伝わったのだろう。ルイス・カルロス・セベリッチに至ってはサンフランシスコはイタリアの村の名前とまで言っていた。もう何が正しいかわからなくなる。
歌の内容から場所が絞れないかと思って調べてみたが、手掛かりになるようなフレーズはなかった。
歌詞
Diré...No tengo miedo...
y diré que este amor ya es de verdad
sabrás que mi destino es
caminar y caminar sin descansar
y cuando llegues al fin del camino
tendrás este amor todo para ti
en San Francisco esa tierra divina
se realizará nuestro porvenir
y tu verás que todos nuestros sueños
se harán realidad.
訳(近藤眞人氏による)
僕は何も怖れてはいない
そしてこの愛が真実だと君に誓う
僕の運命の人だと君も知っているはず
休むことなく歩き続けて
道の終わりにたどり着いたら
この愛をすべて君に捧げる
神聖な土地サンフランシスコで
僕たちの未来が結実する
僕たちの夢が実現する
なんとなくゴダイゴのガンダーラを想起させる。少年時代の作者がサンフランシスコに何かしらのあこがれを抱いていたのだろうか。この曲はフォルクローレの曲としてだけでなく、ギターソロやウエスタン、クンビア、タンゴ、ロックなど様々なジャンルで演奏されている。リチャード・クレ-ダーマンの演奏まである。聞き比べてみるのもおもしろい。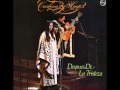 Cristina y Hugo/Camino a San Francisco
Cristina y Hugo/Camino a San Francisco
 作者によるロックバージョン
作者によるロックバージョン
 タンゴバージョン
タンゴバージョン リチャード・クレーダーマン
リチャード・クレーダーマン
- PHURU RUNAS プル・ルーナス/Ramiro de la Zelda
- PHURU RUNAS(プル・ルーナス)は言わずと知れたカルカスのインストの名曲で日本でも定番の演奏曲になっている。初出はCANTO A LA MUJER DE MI PUEBLO(1982)で作者はカルカスの元チャランゴ奏者のRamiro de la Zeldaである。
日本では1984年の来日にあわせてCANTO A LA MUJER DE MI PUEBLOを再編集したレコードがポリドールから発売されていて、その中で竹村淳氏は「プル・ルーナス 本盤ではこれだけがメンバーのオリジナルでなく、ラミロ・デ・ラ・セルダ作のワイニョ。斬新なアレンジと迫力のあるキタスのソロは彼らならではのもの。」と解説していて、タイトルについては触れられていない。その後日本の演奏家の間では曲の紹介において「翼のある人」「鳥人」と訳されることがあったが、カルカスの2009年の来日コンサートで、プログラムに「聖者の翼」と訳され、それが正しいものと私も思っていた。みんなもきっとそうだっただろう。なにせ演奏している本人達の公式見解だから間違うはずないだろうし、曲のイメージにもふさわしく、また、カルカスのロゴの「K」の文字にも翼のある聖人みたいなのが描かれているのもその訳が正しいと納得させる後押しをしていたかもしれない。
ところが2012年11月9日にアップされたこの動画で、MCがPHURU RUNASとは、ケチュア語で「頭に羽毛の帽子をかぶった男」(men with a hat with feathers on his head)の意味と説明している。
 Fortaleza - Phuru Runas (Cable Coffeehouse,Boston 1986)
Fortaleza - Phuru Runas (Cable Coffeehouse,Boston 1986)
参考 Fortalezaのプロフィール
フォルタレサはこの曲の作曲者のRamiro de la zerdaが兄弟のJohn de la ZerdaとGonzalo de la Zerdaと1970年代末に結成したグループで、演奏は1986年のボストンで、この演奏ではラミロはいないものの、ジョンとゴンサロが参加している(チャランゴを弾いているJohn de la Zerdaはこのとき21歳で、6年後の1992年に27歳の若さで亡くなっている)。MCで曲を解説しているのがギター担当のニカラグア人のRoberto Sengelman、もう一人ワンカラをたたいているのが同じくニカラグア人でこの動画をアップしたUlises Huete B.で、この二人は創立メンバーではないが、当然曲の由来などはRamiro de la zerda本人あるいは二人の兄弟から聞いているはずなので、彼の言っていることが間違っていると決めつけることはできない。
実際ケチュア語で「PHURU」を検索してみると翼というより「羽・羽毛」という検索結果がでてくる。ほかにこの曲を演奏している動画についている曲の説明でもPHURU RUNASをスペイン語で"hombres-pluma"と訳しているものがいくつか見られる。hombresは男たち、plumaは羽毛である。
作曲者が存命だから直接本人にメールでもして聞けば一発で解決する問題だけど、さすがにそれは抵抗があるので、想像の域を脱していないが、TobasやTinkuの衣装のような羽飾りを頭に付けた勇ましい男たちの姿を想像すると、曲のイメージと合っているとも言えなくはない。
10 Great Latin American Songs: A Musical Tour of the Region
2023年5月25日に書かれた、「偉大な南米の曲10選」と題されたこのページの4曲目にもプル・ルーナスが取り上げられており、
"phuru runas" comes from the widely understood Quechuan language and simply means "man with a feathered hat on his head."
と説明されている。出典や根拠が書かれていないが参考として挙げておく。この説が一定の支持を受けている一つの証明となるだろう。
ただ、一つだけ懸念があるのは、最初に挙げたフォルタレッサの動画で、MCのRobertoは曲名をプル・ル"マ"スと言っていることである。しかも2回も言っているので言い間違いではないだろう。曲名もきちんと把握していない人が本当にタイトルの意味を理解していたのか若干怪しさを覚えなくもない。
以上で考察を終わりにしようと思ったけど、真実を知りたいという気持ちがだんだん強くなり、ダメもとで返事がなくてもよいからと思って作曲者のRamiroのSNSアカウントにダイレクトメッセージを送ったら、なんとすぐに回答をいただくことができた。間違いがないようにその文章をそのまま掲載する。
Es Hombre adornado con plumas. Si es referente a lo los campesinos bolivianos se adornan con plumas y flores en sus festividades Aymaras en Los Andes de Bolivia
訳すると、 「彼は羽で飾られた男だ。それはボリビアのアンデス山脈で行われるアイマラ族のお祭りで、ボリビアの農民たちが羽や花で身を飾る様子を指している。」ということだ。これにてこの件は締めくくりたい。 - EL MINERO エル・ミネロ/Jaime Medinacelli Ressini
- ボリビアに限らず南米でこの曲を知らない人はいないだろう。言わずと知れたサビア・アンディーナの名曲。作者はこちらもボリビアを代表する大作曲家のJaime Medinacelli Ressini(1911-?)。アルバムの初収録は1980年のDISCOS HERIBA社から発売された"EL MINERO"(SLP-2182)。
いろいろな歌詞がネット上に出回っている中で、自分が比較した結果、次の動画のものがもっとも正しいものだった。
 EL MINERO (letra) - SAVIA ANDINA
EL MINERO (letra) - SAVIA ANDINA
歌詞を文字に起こすと以下とおり。
Sombrios dias de socavon Noches de tragedia
Desesperanza y desilusion Se sienten en mi alma
Asi mi vida pasando voy Por que minero soy
Minero que por mi patria doy Toda mi existencia
Mas en la vida debo sufrir Tanta ingratitud
Mi gran tragedia terminara Muy lejos de aqui
Pre destinado a vivir estoy En el santo cielo
Por eso a Dios le pido morir Como buen minero
Minero kani llaqtaymanta Minero jina kawsakuni
Mana imaypis kapuwanchu Sonqetullayta saqesqayki
Minero manta yuyakunki Minero jina kawsakusaq
Niwarqachari kawsaspari Waqharikuspa ripushkani
私なりに日本語に訳してみたが、意味が通じるように多少強引に日本語にしたので間違っているかもしれない。
坑道の暗黒の日々/悲劇の夜/絶望と失望/私は魂の中でそれらを感じている
私の人生はこのように過ぎていきます/なぜなら私は祖国のために身を捧げる鉱夫だからです
しかし人生において、私はたくさんの恩知らずを負わなければならない
私の大きな悲劇はここから遠く離れたところで終わるでしょう。私は聖なる天国で生きる運命にある
だからこそ、私は優秀な鉱夫として死なせてくださいと神に懇願します。
私はこの土地出身の鉱夫です。私は一人の鉱夫として生きています。私は何も持っていません。私の心だけをあなたに残します。
あなたは鉱夫であることを忘れないでしょう。私は一人の鉱夫として生きていくつもりです。 おそらく彼が生きていたら、私は去ってしまったと泣きながら言うだろう。
以上の訳はケチュア語部分の歌詞をスペイン語に翻訳しているサイトを参照に、さらにそれを日本語化したものである。参考にしたサイトは以下のもの。ケチュア語の最後の一文の訳が納得いく解釈がなかった
ケチュア語→スペイン語 参考サイト Savia Andina El Minero → Spanish translation
 Savia Andina - El Minero ( Subtitulado Quechua - Español ) - Letras y Traducción
Savia Andina - El Minero ( Subtitulado Quechua - Español ) - Letras y Traducción
 Aprende QUECHUA con la canción EL MINERO - Savia Andina
Aprende QUECHUA con la canción EL MINERO - Savia Andina
単純に歌詞と意味が知りたい人はここまで読めば十分なのだが、私が語りたい本題はここからである。Googleなどの検索サイトで"SAVIA ANDINA EL MINERO 歌詞"と入れて検索するとありがたいことに一発で結果がヒットしてくれる。これはとても便利で助かると思ってとびついてしまうと大変なことになる。実はそこにあるものは間違っているからだ。
一番大きな違いはSonqetullayta saqesqaykiのところがSula thullaita sapeskairyとなっているところだが、それ以外にもこまごま微妙に違っているところがある。そして困ったことにこの違った歌詞を採用している動画がたくさんあるのだ。例えば、Youtubeで"EL MINERO KARAOKE"と検索すると3本ほど動画がヒットするが、そのうち2つがこの間違った歌詞を採用してしまっている。音源をよく聞けばそれが間違いだと気づくはずなのだが、意外と気づかないものなのだろうか。
どうして間違った歌詞が流布してしまっているのか不思議だったが謎を解くヒントとなるものを見つけた。それはペルーの歌手のWiliam Lunaがこの曲をカバーして、そのように歌っていたのだ。
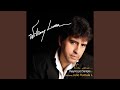 Wiliam Luna EL MINERO
ここから自分の推測は次の通り。サビア・アンディーナのエル・ミネロが流行して、それをウィリアム・ルナがカバーするときにケチュア語部分の歌詞を間違えて聞き取りしてしまう。大物歌手なので南米全体にその歌詞がネットやCDなどに書かれて広まる。同じ曲なのでサビア・アンディーナの元の歌詞も同じと誤解され、ついにはこれがネットでもサビア・アンディーナの歌詞として出回ってしまう。ちなみに同じケチュア語でもボリビアとペルーでは地方差があって、サビア・アンディーナのケチュア語はポトシのそれで、クスコのケチュア語とは発音に違いがある。そういったことも関係しているかも知れない。あるいは聞き間違いでなくペルー人向けのわかりやすいケチュア語になるようにわざとそのように変えたという可能性もある。
Wiliam Luna EL MINERO
ここから自分の推測は次の通り。サビア・アンディーナのエル・ミネロが流行して、それをウィリアム・ルナがカバーするときにケチュア語部分の歌詞を間違えて聞き取りしてしまう。大物歌手なので南米全体にその歌詞がネットやCDなどに書かれて広まる。同じ曲なのでサビア・アンディーナの元の歌詞も同じと誤解され、ついにはこれがネットでもサビア・アンディーナの歌詞として出回ってしまう。ちなみに同じケチュア語でもボリビアとペルーでは地方差があって、サビア・アンディーナのケチュア語はポトシのそれで、クスコのケチュア語とは発音に違いがある。そういったことも関係しているかも知れない。あるいは聞き間違いでなくペルー人向けのわかりやすいケチュア語になるようにわざとそのように変えたという可能性もある。
ウィリアム・ルナがエル・ミネロをカバーしたのは2019年(Huaynos por Siempre vol.1)のことで割と最近のことだ。私が2003年にボリビアで入手したいくつかの歌集ではみなオリジナルと同じ歌詞だった。サビア・アンディーナとウィリアム・ルナの間に40年の隔たりがあるのでその間にすでに別の人が歌詞を変えて歌っていた可能性もあるが、今のところ見つけられていない。ご存じの方がいらっしゃいましたら教えていただきたい。
以上の話はアルバム収録曲に限定している。最近のサビア・アンディーナのコンサートの動画では、ケチュア語のMinero jina kawsakusaq Niwarqachari kawsaspari の部分をMinero jina panpakusaq Siwaqchapuni kawsaspari と変えて歌っている。
 SAVIA ANDINA - El Minero(en vivo)
SAVIA ANDINA - El Minero(en vivo)
 SAVIA ANDINA - EL MINERO(EN VIVO)
SAVIA ANDINA - EL MINERO(EN VIVO)
 Savia Andina - El Minero(Festival Del Bandas 2023)
Savia Andina - El Minero(Festival Del Bandas 2023)
こちらの歌詞で歌っているものを他にも見つけることができた。Maria Luisa Tiradoという女性歌手である。1960年以降に活躍しているポトシ出身の歌手だ。音源は2015年に発売されたベスト盤のもので、オリジナルの音源は見当たらないが、サビア・アンディーナの演奏と酷似しているので、おそらく1980年のサビア・アンディーナの録音より後だと思われる。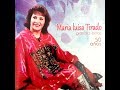 El Minero - Maria Luisa Tirado
El Minero - Maria Luisa Tirado
長年歌っている場合、歌詞が変わることは珍しくないが、そのきっかけになったのがもしかしたらこの録音と関係があるかもしれない。全く関係ないかもしれない。
- EL LLANTO DE MI MADRE /Int.Los Jairas 2023.10.28記
-
ロス・ハイラスの事実上のデビュー曲。
 El llanto de mi madre. Los Jairas 1966
El llanto de mi madre. Los Jairas 1966
Los Jairasは1966年6月に結成され、コチャバンバで開催されたparticipan en el Festival Nacional del Folkore de Boliviaでこの曲を演奏して優勝する。ラウロ・レコードからこの曲と他2曲を収録したAsí triunfaron Los Jairas en el 2º Festival de la Canción Bolivianaが発売される。
参考:https://www.discogs.com/ja/release/22767533-Los-Jairas-Asi-Triunfaron-Los-Jairas-En-El-2do-Festival-De-La-Canci%C3%B3n-Boliviana-1966
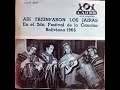 ASÍ TRINUFARON LOS JAIRAS (EP 1966)
ASÍ TRINUFARON LOS JAIRAS (EP 1966)
演奏メンバー
Gilbert Favre (Quena)
Ernesto Cavour (Charango)
Edgar yayo Joffre (Bombo/Voz)
Julio Godoy (Guitarra)
この曲の歌詞はJUAN HUALLPARRIMACHI(フアン・ワルパリマチ)のケチュア語の詩が元になっている。上に挙げた動画の解説欄にはHUALLPARRIMACHIとはケチュア語で「鶏と話す人」という意味とのこと。JUAN HUALLPARRIMACHIについて、Wikipediaの英語版・スペイン語版には以下のように説明されている。
フアン・ワルパリマチ・メイタ(ポトシ、1793年 - 1814年)はボリビアの詩人であり、ケチュア語で著作を書いた独立支持派のゲリラ戦士であった。 彼は人々の伝統に取り組みながら、先住民の言語でデシマ(décima-10行詩)を作成。 彼の仕事は比較的無視されることになった。
バイオグラフィー
ワルパリマチはボリビアのポトシ県チャヤンタ県マチャ村で生まれた。 ポルトガル系ユダヤ人の孫で、ペルーのクスコ出身の先住民の母親とスペイン人の父親の間に生まれた息子だが、二人とも生後間もなく亡くなった。 彼は先住民によって育てられ、後にゲリラのマヌエル・アセンシオ・パディージャとフアナ・アスルドゥイ・デ・パディージャにスカウトされ、彼らとともにスペイン政府と戦った。 彼は母方の祖父の姓しか知らなかったため、メイタ姓を採用した。
彼は1814年のボリビア独立戦争で、指導者であり保護者でもあったフアナ・アスルドゥイの指揮下で戦い、20歳で亡くなった。 彼はボリビア文学における「詩人の兵士」として不滅の存在となった。
参考:WIKIPEDIA
https://en.wikipedia.org/wiki/Juan_Wallparrimachi
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Huallparrimachi
動画によるJUAN WALLPARRIMACHIの解説
 JUAN WALLPARRIMACHI
JUAN WALLPARRIMACHI
ワルパリマチのケチュア語の詩は以下のものだった。10行詩の形式になっている。
Mamay
¿Ima phuyu jaqay phuyu yanayasqajj wasaykamun?
Mamaypajj waqayninchari paraman tukuspa jamun.
Tukuytapis inti k’anchan, ñuqayllatas manapuni.
Tukuypajpis kusi kawsan, ñuqay waqaspallapuni.
Pujyumanta aswan askhata ma rejsispa waqarqani,
mana pipas pichajj kajtin ñuqallatajj millp’urqani.
Yakumanpis urmaykuni, yaku, apallawayña nispa.
Yakupis aquykamuwan, riyrajj, mask’amuyrajj nispa.
Paychus sunquyta rikunman, yawar qhuchapi wayt’asqan,
khiskamanta jarap’asqa pay jinallatajj waqasqan.
動画の解説欄にスペイン語訳も掲載されているので、転載する。
¿Qué nube será esa nube, que ennegrecida se aproxima?
Será tal vez el llanto de mi madre, que en lluvia se ha convertido.
El sol alumbra a todos; a todos, menos a mí.
A nadie le falta dicha; mas para mí sólo hay dolor
Porque no pude conocerla, lloré harto más que la fuente y porque no hubo quien me asista, mi propio llanto bebí.
Entonces al agua me arrojé, diciendo "quiero que me arrastres".
Pero el agua me echó a la orilla diciéndome: "Sigue buscándola".
Mi corazón también lloró, flotando en un lago de sangre,
envuelto en una maraña de espinas, mientras ella está llorando.
日本語に訳してみた。
黒く近づいてくるその雲は何の雲なのだろうか?
雨に変わった母の泣き声かもしれない
太陽はすべての人を照らします。 私を除く全員に。
喜びに欠けている人は誰もいません。 でも私にとっては痛みだけです。
母に会えなかったので涙が溢れ、誰も助けてくれなかったので自分の涙を飲みました。
そして「私を連れて行って」と言って水の中に身を投げました。
しかし、水は私を岸に投げ飛ばし、「母を探し続けなさい」と言いました。
母が泣いている間、私の心も泣いた。
血の湖に浮かんで、絡み合った棘に包まれて。
参考:Adolfo Cáceres Romero氏によるスペイン語訳
“Mamay/Mamá”, Juan Wallparrimachi
¿Qué nube será aquella nube que oscurecida se aproxima?
Será el llanto de mi madre que llega convertida en nube.
A todos ilumina el sol, menos a mí.
A todos les llega la felicidad, en cambio para mí sólo hay dolor.
Más que un manantial al no conocerla me puse a llorar
y no habiendo quien me socorriera mis propias lágrimas bebí.
También a las aguas me arrojé, diciéndoles: – “Aguas, llévenme»
Pero las aguas me arrojaron a la orilla, diciéndome: – “Anda a buscarla».
Si ella pudiera ver en mi corazón, cómo está en un charco de sangre,
enredado entre espinas, llorando al igual que ella.
ロス・ハイラスの曲ではケチュア語の最初の2行をケチュア語-スペイン語で同じ内容で繰り返している。
¿Ima phuyu jaqay phuyu yanayasqa wasaykamun?
¿Que nube es aquella nube negreando viene de vuelta?
mamaypaj waqayninchari paraman tukuspa jamun
sera el llanto de mi madre convertida en lluvia viene
そのあとの歌詞は元の詩にはないヤヨ・ホフレの創作部分である。
descansa en paz madre mio te lo pido de rodillas(bis)
母さん、安らかに眠れ ひざまずいてお願いします。
reza por quien no te olvida nunca y te llora noche y dia(bis)
あなたを決して忘れない人たちのために祈ってください。そして昼も夜もあなたのために泣きます。
曲のタイトルのEl llanto de mi madreは初期のアルバムではDos Amigos (El Llanto De Una Madre)と表記されているのもある(下記画像参照)。
https://www.discogs.com/ja/master/1794173-Los-Jairas-El-Llanto-de-Mi-Madre/image/SW1hZ2U6NDgzOTE2ODM=
https://www.discogs.com/ja/release/15360473-Los-Jairas-Dos-Amigos-El-Llanto-De-Una-Madre/image/SW1hZ2U6NDY2MzU0NTA=
歌詞の内容からDOS AMIGOSはふさわしくない気がするのだけど、なぜそのようなタイトルがついているのか。独自の推論を展開したい。
私が注目する点は、この曲のクレジットである。アルバムによって多少の記述の違いがあり、D.R.とするもの、Dpto.Folkloreとするもの、Departmento Folklore,Letra E.Jofreとするもの、Mus.Depto.Folk.Bol.Let.E.Jofreとするものなどがあるが、共通することは、もともとのメロディがあったと考えられることである。その曲こそがDOS AMIGOSという曲だったのではないだろうか。その曲のメロディにホフレが上記で述べた歌詞をつけたものと考えられる。内容がだいぶ変わってしまったため、DOS AMIGOSというタイトルのままカッコ表記でEl Llanto De Una Madreと附したのではないだろうか。
そこでDOS AMIGOSという曲を探してみたところ、似たメロディの曲を見つけることができた。それが以下の曲である。
 UN YARAVÍ PARA TI Hnos Portugal
UN YARAVÍ PARA TI Hnos Portugal
アルバムデータ
https://www.discogs.com/ja/release/21888940-Hermanos-Portugal-Un-Yarav%C3%8D-Para-T%C3%AD
1972年のペルーのアルバムである。クレジットにはこの曲の作者はMariano Melgarと書いてる。Benigno Ballón Farfánの有名なワルツの曲「詩人メルガール」で歌われている人物である。この人物についてもWikipediaに掲載されている。
https://es.wikipedia.org/wiki/Mariano_Melgar
Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso(アレキパ、1790-1815)はペルーの詩人、独立革命家。poeta de los yaravíes(ヤラビの詩人)として知られる。アメリカにおけるロマン主義文学の先駆者で、本格的なペルー文学の創始者、クリオージャ音楽の先駆者と評されることもある。スペインとの独立戦争のさなか24歳で戦死する。
ただし、このDOS AMIGOSの作曲者が本当にMariano Melgarなのかは根拠が上記のアルバム以外に資料が見あたらないのであまり自信がない。よって本来の作曲者についてはこれ以上述べないでおく。問題はこの曲がハイラスの原曲となっているかどうかである。
比較のため他の演奏も挙げておく。
 yaravi DOS AMIGOS trio yanahuara
yaravi DOS AMIGOS trio yanahuara
こちらもペルーの1970年代の演奏。
 Pedro Humire Loredo - Dos amigos (yaraví, 1985)
Pedro Humire Loredo - Dos amigos (yaraví, 1985)
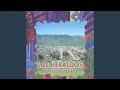 Los Heraldos - Dos amigos
Los Heraldos - Dos amigos
ハイラスの曲のメロディに似ているように思えるが、皆さんにはどのようにとらえられるでしょうか? ハイラス以前の音源はないかだいぶ探したのだけど、確実なものは見つけられなかった。
http://luispareja-fotografia.blogspot.com/2013/12/arequipa-y-su-musica-1913-2013-cien.html
このサイトには1913年9月にケーナ奏者のMariano Escobedoと Domingo Núñezとギター奏者のEmilio SirvasがLos dos amigosという曲を録音したと記されているものの、詳しいことがわからないため、当該曲と断定することができない。
ただ1917年にアレキパで出版された“El Cancionero Mistiano”を引用した1976年に発行されたLuis Guillermo Carpio Muñoz著“El Yaraví Arequipeño. Un estudio histórico-social y un cancionero” にはこの詩が掲載されていたようだ。
http://cantemosperu.blogspot.com/2014/09/2878-dos-amigos-una-tarde-yaravi.html
Dos amigos una tarde,
Lamentábanse su suerte
Uno al otro se decían
Señor, mándanos la muerte
¿ Quién ha visto el fuego helarse
O la ceniza escarcharse ?
¿ Quién ha visto a dos amantes
Sin motivo, separarse ?
¿ Quién ha visto en su bondad
Al volcán lleno de nieve,
Que aparenta frialdad
Aunque por dentro queme ?
También suele suceder
A veces dulce el veneno
Porque acaba con la vida
Del que vive padeciendo
20世紀初めにはアレキパでヤラビの曲として認識されていたことは間違いない。それをヤヨ・ホフレがアレンジしてできたのがこのEL LLANTO DE MI MADREではないだろうか。
「追記」
この歌詞がJuan Huallparrimachiの詩が元になっている前提で話を始めた。それはこの1966年のアルバムが1970年以降に再販されたときに、レコード盤のラベルに「Juan Huallparimachi」との表記が入っていることでも当時の認識であったと考えられる。しかし、脱稿後に知ったFernando Rios氏の著書 "Panpipes & Ponchos: Musical Folklorization and the Rise of the Andean Conjunto Tradition in La Paz, Bolivia(オックスフォード大学出版局、2020年)"第7章 Los Jairas, Peña Naira, and the Folklore Boomの"El Llanto De Mi Madre"の項によると、ワルパリマチを神格化するあまり、作者不明の12篇の詩を彼の著述にしてしまったと指摘する。これについてはラテンアメリカ文学の研究者に考察を委ねたい。
この書籍は第7章でLOS JAIRASについて詳しく書かれており、さらにEl Llanto De Mi Madreだけで1節を割いている。その中でDOS AMIGOSがEl Llanto De Mi Madreの既存のメロディの正式な名前であることを、Julia Elena Fortún女史がハイラスに伝えていたことを紹介している。もっと早くこの書物を見つけていれば、こんな苦労しなくて済んだのに。とほほ~。
以上「2024.9.26および10.1追記」
その他のEL LLANTO DE MI MADREの演奏動画
 DOLY PRINCIPE Y EDITH RAMOS
DOLY PRINCIPE Y EDITH RAMOS
ヤヨ・ホフレのスペイン語歌詞と違うところもある。この動画についての解説。
https://www.facebook.com/watch/?v=2238419449749956
 DUO SENTIMIENTO
DUO SENTIMIENTO
 GRUPO SEMILLA HD (VIDEO OFICIAL)
GRUPO SEMILLA HD (VIDEO OFICIAL)
 ALFREDO COCA,ALEJANDRO HUANCA
ALFREDO COCA,ALEJANDRO HUANCA
 SANKARA-Ima Phuyu Jaqay Puhyu
SANKARA-Ima Phuyu Jaqay Puhyu
 Ensamble Andino & Wilson Molina
Ensamble Andino & Wilson Molina
 Fernando Chepo Sepulveda
Fernando Chepo Sepulveda
 EL LLANTO DE MI MADRE - Tutorial Completo
EL LLANTO DE MI MADRE - Tutorial Completo
- アンデスの祭り / 作詞:岩沢千早 作曲:ボリビア民謡 編曲:原 由多加/大熊崇子 合奏編曲
-
平成4年(1992年)から教育芸術社発行の『小学生の音楽6』に「アンデスの祭り」という曲が掲載された。平成生まれでこの教科書を使っていたなら習った人も多いと思う。残念ながら現在は外されてしまったようで、令和6年現在は「コンドルは飛んで行く」が掲載されている。
曲名をYoutubeで検索すればいろいろ出てくるので、ここでは1つだけ掲載する。
 アンデスの祭り
アンデスの祭り
太鼓をならし ケーナを吹いて
行列が行く 緑の谷へ
真っ赤な仮面 綺麗なポンチョ
大きな帽子 ゆらゆらゆれる
ほらほら踊れ 今日は祭りアンデスの春
ほらほら踊れ 今日は祭りアンデスの春
ラララララ…
太鼓をならし ケーナを吹いて
行列が行く 緑の谷へ
黄色い仮面 綺麗な衣裳
小さな飾り きらきらひかる
ほらほら踊れ 今日は祭りアンデスの春
ほらほら踊れ 今日は祭りアンデスの春
フォルクローレを演奏する人であれば、後半部分つまり「ほらほら踊れ」以降は有名な「ラ・マリポーサ(蝶々)」という曲だと気づくだろう。しかし前半の「太鼓をならし」からの4行のメロディは何の曲か、出典は何だろうか。
結論を先に言えば、出典はキングレコードの「アンデスの祭りと踊り~ボリビアとペルーの伝統音楽~」(Barclay,GT-5010,1973年)に収録されている、1曲目の「オルーロのカルナバリート」中の7分30秒から流れるメロディーがこれに相当する(齋藤征範氏のご教示による。フォルクローレQ&Aより)。
アルバムのジャケット裏解説には、「オルーロのカルナバリート(ディアブラーダ)CARNAVAL D ORURO」と書かれている。フランス語が書かれているのは後述するようにこのアルバムの元アルバムがフランス盤だからである。
参考画像
アルバムジャケット裏
アルバム音源
 Los Indios del Sol (1971)
Los Indios del Sol (1971)
教科書に掲載されたこの曲の出典について、DIC談話室の常連のじゅら♪さんがこの教科書の会社に問い合わをしたところ、編曲者に確認の上での回答として「オルロ市のカーニバルで演奏されるディアブラーダ」が原曲だとの回答があったそうだ。なぜモレナーダでなくディアブラーダなのかという謎は、このアルバムジャケット裏にディアブラーダと書いてあることをそのまま答えたからなのだろう。
さらに「アンデスの祭り」をJASRACで検索すると作品タイトルにCARNAVALITO D ORUROとあることからもこれが元音源であることは間違いないだろう。
このアルバムはフランスのバークレイ社が1970年に発売した Gérard Civet – Découvrez La Bolivie & Le Pérou "Indios Del Sol" というアルバムが元になっている。Gérard Civetという人が現地録音と解説を書いている。そしてこのレコードと同名の"Les Indiens Du Soleil"という著書も出版している(1974年)。
Les Indiens du soleil / Gérard Civet, Chantal Manoncourt
次にラ・マリポーサの出生の秘密に迫りたい。
ラ・マリポーサが作曲された経緯について、FacebookのMoreno Bolivianoの2021年6月11日の投稿記事についたコメントに次のようにある。
https://www.facebook.com/MorenoBolivianoHeyHey/posts/pfbid0xWWecAhL5FfbF4gNCfczegCSywC4UUBFs2B8CsU4RTbgezSXuimyjo1xMZJwXUadl
La MARIPOSA nace a partir de una pinkillada de Achacachi, recopilada por Gumercindo Licidio y arreglos de Andrés Rojas Quierberth en 1967, grabada en 1969 por la Banda Pagador en ritmo de Morenada,
※QuierberthとあるのはQuisbertの誤りである。
<訳>ラ・マリポーサはアチャカチのPinkilladaから生まれ、1967年にグメルシンド・リシーディオとアンドレス・ロハス・キスベルトが採譜し、1969年にバンダ・パガドールによってモレナダのリズムで録音された。
Gumercindo Licidio Chambi(1931-2013)は1964年6月9日にバンダの楽団"PAGADOR DE ORURO"を創設した人物で、Andrés Rojas Quisbert(1938-2019)はラパス近郊のデサグアデロ出身の作曲家・演奏家である。アチャカチ村のピンキジャーダが原曲かどうかは不確かで、あるいはこの発言はモレナーダの起源そのもののことを言っているのかもしれない。
このとき録音されたアルバムというのは、次のレコードであろう。
La Banda Pagador De Oruro – Mas Exitos De Morenadas Con La Banda Pagador De Oruro(Discos Titikaka – EP. JCH-101)
https://www.discogs.com/ja/release/23546393
製造年は記されていない。DISCOS TITIKAKAというのはラパスのレーベルで、1960年代後半からレコードを作製しているようだが、DISCOGSにも10数枚しかデータが載っておらず、そのほとんどが年代不詳となっている。
https://www.discogs.com/ja/label/1433166-Discos-Titikaka
ANTOLOGÍA DE LA MORENADA CENTRAL (Comunidad Cocanis) というアルバムの動画で、概要欄にそれぞれの曲が発表された年が記載されていて、17分26秒からのラ・マリポーサは1969年と書かれている。この記述はJosé Flores Orosco(El Jach'a)氏の10年にわたる研究の成果であると記されており、信頼に足るものと考える。
 ANTOLOGÍA DE LA MORENADA CENTRAL (Comunidad Cocanis) - JOSÉ JACH'A FLORES & CARLOS REYNOLDS
ANTOLOGÍA DE LA MORENADA CENTRAL (Comunidad Cocanis) - JOSÉ JACH'A FLORES & CARLOS REYNOLDS
FacebookのグループOruro en Fotografías Antiguas. "La máquina del tiempo"に2018年12月7日に投稿された記事によると、"PAGADOR DE ORURO"によるラ・マリポーサの初演が1970年だったとある。また、ラ・マリポーサという曲名の由来はMorenada Zona Norte(1913年設立の有名な踊りのグループ)が蝶の形をしたマトラカを使用していたことが由来となっていると書かれている。 Oruro en Fotografías Antiguas. "La máquina del tiempo"
参考:Más de 100 años con la Morenada "Zona Norte"の該当箇所を翻訳する。
「私たちが、アルパの形をした古いマトラカを置き換えるために、新しいマトラカの形として蝶々をリハーサルに持ってきたところ、たまたまグメルシンド・リシディオがその場に顔を出し、彼はならず者(あるいは「すごい奴」)だったから、**『俺が「マリポーサ(蝶々)」という曲を出し、それで終わりだ(文句は言わせない)』**と言った。」
参考:2003年のPAGADOR DE ORURO 50周年演奏
 Morenada La Mariposa 2003, Mejillones Oruro - BANDA ESPECTACULAR PAGADOR DE ORURO BOLIVIA
Morenada La Mariposa 2003, Mejillones Oruro - BANDA ESPECTACULAR PAGADOR DE ORURO BOLIVIA
1969年にはLOS PAYASがCantando Con Banda "La Mariposa"というアルバムでBANDAの演奏とともに歌っているアルバムを出している(LYRA,EPL250)。ジャケット裏には伴奏がBanda de Javierito Illanesだったと記載されている。レコード本体のクレジットには、Gumercindo Licidio,Andrés R.と二人の名が記されている。
 LOS PAYAS - La Mariposa
LOS PAYAS - La Mariposa
参考:DISCOGSアルバムデータ(Lyra EPL-250,1969/12/3)
https://www.discogs.com/ja/release/25315348-Los-Payas-Cantando-Con-Banda-La-Mariposa
LOS ZIG ZAG (de Sucre)もコチャバンバ市のRCA Victorで1969年半ばに録音したという記述がある(動画概要欄)。歌詞はついていない。
 LOS ZIG ZAG (Sucre) 1969. Disco Completo
LOS ZIG ZAG (Sucre) 1969. Disco Completo
参考:DISCOGSアルバムデータ(RCA Victor BOH-024,1969)
https://www.discogs.com/ja/release/11186047-Los-Zig-Zag-De-Sucre-Se%C3%B1ora-Chichera
Carlitos Peredo – Color Y Ritmo De Bolivia これも歌詞はついていない。
 Carlitos Peredo LA MARIPOSA
Carlitos Peredo LA MARIPOSA
参考:DISCOGSアルバムデータ(Lyra LPL-13092,1969/12/18)
https://www.discogs.com/ja/release/11212656-Carlitos-Peredo-Color-Y-Ritmo-De-Bolivia
Los Sicuris Del Altiplano – Los Sicuris Del Altiplano 「Mariposa - Morenada Gumercindo Licidio」と記される。インストルメンタル。
 La Mariposa - Morenada Boliviana
La Mariposa - Morenada Boliviana
 LOS SICURIS DEL ALTIPLANO (1969)フル
LOS SICURIS DEL ALTIPLANO (1969)フル
参考:DISCOGSアルバムデータ(Lyra SLPL-13096,1969)
https://www.discogs.com/ja/release/19673101-Los-Sicuris-Del-Altiplano-Los-Sicuris-Del-Altiplano
Fidel Magno – Sampoñas Del Huracan(Impacto-0532,1969)クレジットには「Morenada Versos F.Magno」とある。ボーカルのFidel Magnoが独自の歌詞をつけている。
 Zampoñas Del Huracan- Mariposa
Zampoñas Del Huracan- Mariposa
参考:DISCOGSアルバムデータ(Impacto-0532,1969)
https://www.discogs.com/ja/release/18567550-Fidel-Magno-Sampo%C3%B1as-Del-Huracan-
以下は音源は確認できなかったがそれらしいと思われるもの。
Raul Rojas Y Su Orquesta /Raul Rojas Y Su Orquesta Vol.2(Impacto-0523,1969)にはMARIPOSA Morenada D.R.とある。
https://www.discogs.com/ja/release/16467603-Raul-Rojas-Y-Su-Orquesta-Raul-Rojas-Y-Su-Orquesta-Vol-2
La Orquesta De Jazz De Oscar Loayza – No Quiero Felicidades(Disc.Andino EP-CC040,1969/11/27)「(morenada)Der.Res.」とある。
https://www.discogs.com/ja/release/22718162-La-Orquesta-De-Jazz-De-Oscar-Loayza-No-Quiero-Felicidades
Los Hijos Del Pagador – La Mariposa, Basta Vidita / Tincu, Carnaval (Lauro,CDLR-5342)
https://www.discogs.com/de/release/28604689-Los-Hijos-Del-Pagador-La-Mariposa-Basta-Vidita-Tincu-Carnaval
発売年は不明。Pagadorは一般には「支払う人」という意味だが、ボリビア、ことにオルロでは1781年2月に起こったスペイン植民地支配に対するオルロの反乱の主導者のセバスティアン・パガドールのことを指す。
日本人演奏家がよく手本にするInti-IllimaniのLa Mariposaは1970年に発表された。歌詞はなくララララの所だけうたって、あとはケーナで吹いている。
 Inti-Illimani - La Mariposa
Inti-Illimani - La Mariposa
https://www.discogs.com/ja/master/991698-Inti-Illimani-Inti-Illimani-C%C3%B3ndores-Del-Sol
以上の経緯をまとめると、ラ・マリポーサは1969年に録音され、レコードが発売されるやたちまち広まり、さまざまなグループがアルバムに収録した。そして翌年にはフランス人のGérard Civetがバンダの演奏を録音し、フランスでレコード化したという流れが見えてくる。ただ、結局誰の演奏かは確定できない。すでに1970年にはPagador de Oruro以外の多くの楽団が演奏していただろうから、その判別は難しいであろう。
以下は話題がずれてしまっているので暇な方のみお読みください。
ここまではうまく話が進んできたのだが、ここで看過できない問題が発生してしまった。それはLOS CHASKASタイムリープ問題である。どういうわけか、CHASKASの1965年のアルバムにこのLA MARIPOSAが収録されている。「それは年代が間違っているだけではないのか?」と一蹴したいところだが、このアルバムを紹介している全てのサイトが1965年としているのでこちらもそれなりの反論の根拠を挙げなければならないだろう。
まず1965年とするサイトを紹介する。
まずはYotubeのトピックである。
 LOS CHASKAS - La Mariposa
LOS CHASKAS - La Mariposa
動画の概要欄にはアルバム収録年を1965年と記している。
次いでYoutubeにアルバムをフルサイズでアップしているJean Jacques氏である。
 LOS CHASKAS .....(1965) .....Sello RCA VICTOR BOL/S-014
LOS CHASKAS .....(1965) .....Sello RCA VICTOR BOL/S-014
ここに書かれている RCA VICTOR BOL/S-014をDISCOGSで確認してみると、
https://www.discogs.com/ja/release/8226024-Los-Chaskas-Los-Chaskas
やはり1965年となっている。アルバムのジャケットやレコード本体には製作年は書かれていない。
以下のサイトも同じく1965年としている。
https://musicaandina2011.blogspot.com/2020/03/los-chaskas.html
https://folklorenoaargento.blogspot.com/2018/01/los-chaskas-su-primer-album-larga.html
https://andesnevados.blogspot.com/2017/09/los-chaskas-lp-1965.html
このように多くのサイトでそろって1965年としているのだから、それを否定するならこちらもそれなりに論理を重ねていかなければならない。
まず、チャスカスの名前がいつから用いられたかを考えたい。これについては実は命名した人物がわかっている。上に挙げたmusicaandina2011.blogspotのサイトには名前の由来が次のように書いてある。
Los Chaskas comenzaron a tocar con un grupo de amigos de un elenco de ballet folklórico, en una época en la que los sonidos de las quenas o zampoñas no estaban de moda. Al principio se hacían llamar "Los Jóvenes del Folklore", pero el presentador de la radio Méndez Micky Jiménez, los bautizó como "Los Chaskas" por la costumbre de llevar el cabello largo.
これによると、もともとは"Los Jóvenes del Folklore"(フォルクローレの若者たち)と名乗っていたのだが、ラジオ番組に出演した際に、彼らが長髪だったことから番組の司会者のMicky JiménezがLOS CHASKASと命名したとのことだ。CHASKAには「明けの明星」という意味のほかに「ぼさぼさ髪の男たち」という意味があるらしい(Fernando Rios氏著書第7章New Andean Conjuntosの節)。ここからさらに調べていくと次の新聞記事が見つかった。ラパスの新聞LA RAZONの2015年4月7日のチャスカスのコンサートの告知の記事である。
https://dev-qa.la-razon.com/la-revista/2015/04/07/los-chaskas-tocan-gratis-en-el-teatro-municipal/
“Fue en el año 1966 en La Paz, en el programa El show de los sábados, conducido por Miki Jiménez, donde nos bautizamos como los ch’askosos y después adquirimos el nombre de Ch’askas”, se cuenta en la nota de prensa de la agrupación.
ここには、1966年に"El show de los sábados"という番組で司会のMiki JiménezからLOS CHASKASと命名されたと書かれている。2つの記述に矛盾がないことから、チャスカスの名前は1966年から使われたと考えてよいだろう。2000年のアルバム(DISCOLANDIA,CD-LE-533,D.L.4-4-64-00)のライナーノーツに創設を"Un dia 22 de julio de 1966"(1966年7月22日)と書いてあるが、あるいはこの出来事がこの日だったのかもしれない。名前が付けられたのが1966年であるなら1965年にその名を冠したアルバムが存在するのはおかしい。
なお、テイクオフから出た2枚組CD「LOS CHASKAS ETERNOS」(TKF9701,1997年)のエルネスト河本氏の解説では、結成を1967年7月16日としている。この日についてチャスカスの記事を調べてみたが、何も見つからなかった。さらにFernando Rios氏の著書では1968年に結成して、1年後にはボリビアを代表する人気バンドになったと述べられている。いずれにしても1965年以降である。
次にアルバムのNoであるBOL/S-014という番号から考えてみよう。この番号はRCA Victor社がボリビアでレコードを発行するときにBOXX-XXXのように通し番号を振っている。BOのあとのLはプレスメーカーであったLauroのLであろう。/Sはステレオの場合に記される。このアルバムの一つ前の番号であるBOL-013のアルバムが何年に発行されたかがわかれば、およその時期が特定できるのではないだろうか。そこでグーグルの検索フィールドに「RCA VICTOR BOL-013」と入力して祈ると祈りが通じたのか次のアルバムが見つかった。
https://www.discogs.com/ja/release/12397883-Trio-Los-Cambitas-Camba-Trovador
TRIO LOS CAMBITASというグループである。残念ながら発行年は書かれていないが、グループとアルバム名がわかれば、そこからさらに検索をしていけばよい。すると、以前ヤフオクで出品された時のジャケットや盤面が確認できるものの、やはり年代はわからない。そもそもこの頃のレコードはジャケットやレコード本体に製作年を印字しない。だからいろいろ困る状況になっているのだ。
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/f1094202759
しかし、Youtubeでアルバムを検索してみるとBoris Vargasという人がこのアルバムの曲をアップしていて、1969年と付記しているのが見つかった。
 LOS CAMBITAS (1969) Mis versos a ti
LOS CAMBITAS (1969) Mis versos a ti
同じ手法で一つ後の番号のBOL-015も検索してみたが、見つからず、その次のBOL-016でLOS CUNUMISというグループがヒットした。
https://www.ebay.com/itm/154564875928
該当するアルバムを探すと次のページが見つかった。これにより1970年のアルバムと判明する。
https://www.facebook.com/watch/?v=551455783783064
ここからBOL-013の1969年とBOL-016の1970年の間である可能性が濃厚となった。
次はこのアルバムの収録曲から考えていきたい。B面2曲目に収録されている"Cuesta de Sama"というNilo Sorucoの曲がある。Nilo Sorucoがこの曲を発表したのがいつかは調べがつかなかったが、初出は1969年12月で、ほぼ同時に3人のアーチストがそれぞれアルバムに収録し、少し遅れて翌年1月にもう1人のアーチストが発表している。
Jose Zapata (1969年12月3日)
Zulma Yugar Y Coro De La U.M.S.A (1969年12月6日)
Los Copleros Del Sauzal (1969年12月9日)
Carlitos Peredo (1970年1月23日)
このように同じ曲を複数のアーチストが同時期にカバーするのは、単に偶然なのではなく、著名な人物の新曲だからとか、巷でブームになっているとか、何かしらのきっかけが存在することが経験上多い。ラ・マリポーサがまさにその好例である。そしてチャスカスも負けじとCuesta de Samaをアルバムに採用するという経緯を想像するなら、それを収録したアルバムの発行もやはり1969年以後にならざるを得ないだろう。しかし、これは逆の可能性もあり、チャスカスのアルバムがこの4者のアルバムに先行した可能性も否定できない。ただ、その場合でも先ほど述べたのと同様の理由から1969年12月からさほど遡る可能性は少なく、それこそ1965年まで遡ることは難しいように思える。
屋上屋を架すことになるが、もう一つ1965年を否定する根拠を述べたい。それはジャケット裏面最下段に書かれているオフィスの電話番号である。チャスカスのアルバムには以下のように印刷されている。
ジャケット裏画像
一番最後の電話番号に注目して欲しい。これはサンタクルス市にあるアヤクチョ通り235番地のLAUROのオフィスの電話番号が「2-5130」であることを意味している。ところが1968年までに発行された他のアルバムの電話番号は"2-"がなく、ただの「5130」としか書かれていない。
https://www.discogs.com/ja/release/17757550-Armando-Manzanero-Somos-NoviosSiempre-Novios/image/SW1hZ2U6NTU5Njg1NDc=
https://www.discogs.com/ja/release/13907435-Los-Iracundos-Felicidad-Felicidad/image/SW1hZ2U6NDExODkyMjc=
https://www.discogs.com/ja/release/15167543-Palito-Ortega-El-Creador/image/SW1hZ2U6NDU5MTQyMDY=
https://www.discogs.com/ja/release/9464901-Los-Dandys-Dulce-Quincea%C3%B1era/image/SW1hZ2U6MjU5NjcyNjc=
1970年以後の印刷では「2-5130」あるいは「5-5130」に変わっているのである。"2-"と"5-"の2種類ある理由は詳らかでない。"2-"と"5-"の並存が複数年、複数枚存在することから誤植ではないだろう。
https://www.discogs.com/ja/release/14284701-Various-Las-Finalistas-Del-Festival-De-San-Remo-1971/image/SW1hZ2U6NDI1NzgyMzE=
https://www.discogs.com/ja/release/13182608-Los-Chaskas-Los-Chaskas-Y-Su-Nuevo-Sonido/image/SW1hZ2U6Mzg1MTEyMjQ=
肝心の1969年のアルバムが見つからないのが痛恨の極みである。いや、アルバムはあるのだが、オフィスの住所表記が印刷されていない。1969年だけかたくなに住所を隠しているかのようである。
https://www.discogs.com/ja/release/24018365-Celestino-Campos-Notas-Musicales-En-Charango/image/SW1hZ2U6ODE0MDk3ODc=
https://www.discogs.com/ja/release/19795114-Los-Embajadores-Del-Guadalquivir-Homenaje-al-%C3%91ato-Vargas/image/SW1hZ2U6NjQwNzE0MDk=
https://www.discogs.com/ja/release/10449107-D%C3%BAo-Las-Florecillas-Del-Altiplano-D%C3%BAo-Las-Florecillas-Del-Altiplano/image/SW1hZ2U6MjkwMzA2MDY=
1970年以降の電話番号の頭に2or5が付くのは、かつて平成3年(1991年)に東京03局内の電話番号が7桁から8桁に変わったように契約者が増加したために桁数を増やしたのだと考えられる。仮に4桁から5桁の変更がサンタクルスの電話事情が理由でなかったとしても、電話番号表記が変化したことは事実である。重要なのは、この場合、桁数が増えることがあっても減ることはないということ、つまり2-5130から5130に戻ることは決してないのである。これが何を意味するかというと、時系列が確定するということである。つまり、「2-5130」が決して1968年以前には存在することはなく、「5130」が1970年以後に存在することもないのである。
ただし、重版の場合は例外となってしまう。なぜなら古い電話番号のままで販売するわけにはいかないから、そこは修正されるだろう。だから1965年に出たチャスカスのアルバムがあって、それが1970年以降に重版された場合、そこには最新の電話番号が印刷しなおされるだろう。実際には電話番号だけでなくジャケットのデザインも一新されている。
例えばロス・ハイラスの1966年のアルバムにはジャケット違いが存在し、電話番号が「5130」の時のものと「5-5130」となっているものがある。
LPLR1049「5130」表記の例
https://www.discogs.com/ja/release/9667033-Los-Jairas-Los-Jairas/image/SW1hZ2U6MjY1NjI4ODI=
LPLR1049「5-5130」表記の例
https://www.discogs.com/ja/release/16551555-Los-Jairas-Los-Jairas/image/SW1hZ2U6NTEyNDYwMjc=
前者が1970年以前に発売されたアルバム、後者が1970年以後に発売されたアルバムであろう。
もう一つ、上がBOL-004と下がBOL/S-004。電話番号以外にもモノラルからステレオに変わっていることからも変遷を感じることができる。
https://www.discogs.com/ja/release/16236526-Hugo-Barrancos-Kaluyos-Con-Hugo-Barrancos-Y-Su-Guitarra/image/SW1hZ2U6NTAwMDI4Nzc=
https://www.discogs.com/ja/release/22607084-Hugo-Barrancos-Kaluyos-Con-Hugo-Barrancos-Y-Su-Guitarra/image/SW1hZ2U6NzU0NTgwMTg=
このように「2-5130」のアルバムが重版であることを証明するには、それ以前の電話番号表記のアルバムの存在が認められなければならない。チャスカスのアルバムに関しては私としてはないものを証明することはできないという立場になる。
初期のころは形式が定まっていなかったのか、番地表示のみで電話番号が記されていないアルバムも並存する。知っておくと今後何かの役に立つかもしれない。
LED SOCKS 1967年
https://www.discogs.com/ja/release/13916600-Los-Red-Socks-Cicatrices/image/SW1hZ2U6NDEyMjQyNzE=
LOS JAIRAS 1968年
https://www.discogs.com/ja/release/15360473-Los-Jairas-Dos-Amigos-El-Llanto-De-Una-Madre/image/SW1hZ2U6NDY2MzU0ODE=
確認のため014の前後のアルバムも見てみよう。前述の013のTRIO LOS CAMBITASにはジャケット裏に住所表記がないが、BOL-016のLOS CUNUMISには、同様の住所表記が見られる。はたしてどのようになっているだろうか。014のチャスカスのアルバムが5桁表記であるからその後のBOL-016も当然5桁表記でなければならない。その結果は以下のとおりである。
https://i.ebayimg.com/images/g/aFkAAOSwvrxhEuXz/s-l960.webp
電話番号は推測どおり「2-5130」となっているので、この考え方は間違ってなさそうだ。
さらに1976年くらいからは住所表記のレイアウトがジャケット裏の左下に移動している。当該アルバムはそうなっていないことから1976年を下限とみることもできる。
https://www.discogs.com/ja/release/15076949-Los-Chalchaleros-Con-El-Bandone%C3%B3n-De-Dino-Saluzzi-La-Cerrillana/image/SW1hZ2U6NTU5NzE3MDk=
https://www.discogs.com/ja/master/1836556-Katunga-El-Quinteto-Del-A%C3%B1o/image/SW1hZ2U6NDk3NjA3ODI=
話はこれで終わりではない。実はこのアルバムには2種類のシングル盤が存在する。一つ目はアルバムからTendrás Un Altar、Aguilita Voladora、Huayños Pampeñosの3曲が選ばれている。
BOH-022 Los Chaskas – Tendrás Un Altar 年代不詳
https://www.discogs.com/ja/release/22622558-Los-Chaskas-Tendr%C3%A1s-Un-Altar-Aguilita-Voladora-Huay%C3%B1os-Pampe%C3%B1os
https://www.discogs.com/ja/release/24709232-Los-Chaskas-Tendr%C3%A1s-Un-Altar
https://www.discogs.com/ja/master/2862322-Los-Chaskas-Tendr%C3%A1s-Un-Altar
少し上の方でLOS ZIG ZAGというグループが1969年にLA MARIPOSAを録音していることを述べたが、そのアルバムがBOH-024だった。そうなるとBOH-022もこれと近い時期に発売された可能性が非常に高い。次いでもう一つのシングル盤はこちらである。A面にLA MARIPOSA、B面に先述したCUESTA DE SAMAが収められている。 Los Chaskas – La Mariposa / Cuesta De Sama(RCA Victor BOC-007)。それが以下のアルバムである。
https://www.discogs.com/ja/release/14904634-Los-Chaskas-La-Mariposa-Cuesta-De-Sama
DISCOGSでは1965年の発行とするが、この2曲が1969年より前に収録されたとは考えられないことはすでに述べた通りである。ところでLPと2枚のシングル盤の発売に時間差はあるのだろうか?
チャスカスの他のアルバムで確認すると、例えば1970年のアルバムBOL/S-020からVirginia 、Pretenciosa、Recuerdo 、Hacia El Socavon の4曲を抽出したアルバムが同1970年に出ている。
https://www.discogs.com/ja/release/12592913-Los-Chaskas-Los-Chaskas
1981年のアルバムもシングル盤と同年に発売されており、基本的にはこれと同じだったと考える。
https://www.discogs.com/ja/release/13207789-Los-Chaskas-Todos-Juntos
https://www.discogs.com/ja/release/10776132-Los-Chaskas-Reencuento-De
以上、グループの命名時期、アルバムのナンバー、収録曲、ジャケット裏の電話番号表記、シングル盤の存在の5点から1965年にチャスカスのアルバムが出たとは考えられず、1969年以降の可能性が高いことを述べた。しかも翌1970年にRCA Victorから先述のBOL/S-020"Los Chaskas Y Su Nuevo Sonido"が出ていることから1969年から1970年の間の2年間の範囲だと結論付ける。
なぜそれが1965年と認識されるようになってしまったのか? 理由はわからないが、まずどこかのサイトが先に間違えたのを、他のサイトが追随して広がっていったのではないだろうか。自分もよく引用元を鵜呑みにして間違えることがあるのでよくわかる。ネットって怖い。
もう一つ気になるアルバムがある。RCA VictorのBOL-009のナンバリングのもので、BOL/S-014よりだいぶ小さい数字である。だとしたらこちらの方が早く発売されていて、それも1960年代にまで遡る可能性がある。はたしてどうだろうか。
https://www.discogs.com/ja/release/15054023-Los-Chaskas-Tejiendo-El-Folklore
DISCOGSにはジャケット表の写真のみだが、ebayではジャケット裏の写真も掲載されている。残念なことに電話番号表記がないので、年代を推測することができない。
https://i.ebayimg.com/images/g/SWEAAOSwpdpVZLH1/s-l1600.webp
曲順が違うものの、以下のアルバムと内容は同じである。
https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kVRGT4yAmWE0bGDGd_2Txp4bYByV5qXnQ
ここに収録されているTroteという曲はErnesto Cavour作曲のCanto del Viento(風の詩)で、オリジナルのアルバム収録は1973年である。
https://www.discogs.com/ja/release/10822327-Ernesto-Cavour-Ernesto-Cavour-Y-Su-Charango
本家よりカバーの方が先にアルバム化されることはしばしばあるが、それでもオリジナル演奏を大きく遡ることは考えにくいので誤差の範囲と考えてよいだろう。よってこのアルバムは早くて1973年以降のものと考える(Youtubeやmusicaandina2011.blogspotでは1977年としている)。1970年代の発売なのに009の番号を使用した理由はわからない。
ここまで調べてきて、自論に都合の悪いアルバムを見つけてしまった。
Los Fenix BOL-019 年代不詳のアルバムである。
https://www.discogs.com/ja/release/16007190-Los-Fenix-Los-
チャスカスの1970年のアルバムBOL/S-020のひとつ前の番号のアルバムだ。このアルバムのジャケット裏の電話番号が「5130」表記になっている。番号順に発売されているならば、BOL-016「2-5130」→BOL-019「5130」→BOL/S-020「5-5130」と、BOL-019が逆行してしまっていることになる。BOL-009とは逆のパターンでこれだけ1969年以前に発売されたという強引な解釈も頭によぎったが、このアルバムにも G.Licidioとクレジットされたラ・マリポーサが収録されている(どんだけブームだったんだ!?)ことから1969年以降と考えないといままでの論がすべてひっくりかえってしまう。それならやはりBOL-019の電話番号は「2-」か「5-」が印刷されていないとおかしい。論理を組み立てなおさなくてはならないかもしれないが、情報が少なくて良い解決案がでてこない。これ以上考えてもきりがないので、ここで一旦終了としたい。
参考
齋藤征範氏Facebook2024年7月13日の書き込み
齋藤征範氏Facebook2024年9月7日の書き込み
齋藤征範氏Facebook2024年9月10日の書き込み
(2024/9/26記)
- コモ・ア・セチョ COMO HAS HECHO / Letra y Música :Rómulo Flores Delgado, Int.GRUPO TIEMPO
-
個人的に好きな曲なので取り上げる。この曲のオリジナル音源は長年不明だったが、インターネットの発展によって、ネット上で聴くことが可能になった。
COMO HAS HECHOのオリジナル GRUPO TIEMPO(1980年)。作曲はポトシの演奏家Rómulo Flores。
 Grupo Tiempo - Como has hecho
Grupo Tiempo - Como has hecho
削除対策用予備動画
 GRUPO TIEMPO "Como Has Hecho" (1980)
GRUPO TIEMPO "Como Has Hecho" (1980)
歌詞は以下の通りである。他のグループとは歌詞が異なる場合があるので注意。
Debi saber que al amarte yo me perdia
debi saber que tu mundo ya no era mio,
no es tan lejano aquel dia en que me decias
ya no soy niña no juego con sentimiento
como has hecho para amarte asi
como has hecho que te quiera asi
como has hecho me mata tu amor
como has hecho, como has hecho
Al saberte ajena a mis sentimientos
deseo preguntarte que has hecho en mi
la la la la la....
意訳
君を愛した時から、ぼくは自分を見失っていたことを知るべきだった
君の世界がぼくのものでないことを知るべきだった
君はぼくに その日はそんなに遠い日のことではないと
わたしはもう子どもじゃないと もう感情に流されないと言った
ぼくがこんなに君を愛するのは、君がぼくに何をしたからだろうか?
ぼくがこんなに苦しんでいるのは、君がぼくに何をしたからだろうか?
教えておくれ、君がぼくに何をしたのか
君は何をしたのか 君は何をしたのか
君はぼくの気持ちなんか気づこうとしない
君がぼくに何をしたのか、君に尋ねたい
ライライラ・・・・
レコードの歪みのせいも多少あるだろうが40年以上経た今聴くとなかなかひどい演奏である。まさかこの曲が南米全土に知られるほどのヒット曲になるとは、当時誰も考えていなかったであろう。リズムはsayaとなっているが、今現在ではCaporalと言い換えるべきだろう。
2021年にPROYECCIONのチャランギスタのAriel Villazonが作曲者のRómulo Floresにインタビューをしている貴重な動画がある。
 FULL ENTREVISTA A RÓMULO FLORES el compositor de grandes temas como Como has hecho, Tu Partida, y muchas mas
FULL ENTREVISTA A RÓMULO FLORES el compositor de grandes temas como Como has hecho, Tu Partida, y muchas mas
このインタビューによると、1980年にオルーロのフェスティバルに出場するためにGRUPO TIEMPOを結成し、そこでCOMO HAS HECHOを演奏したとのこと。メンバーはほかに、のちにカルカスのメンバーにもなるEduardo YañesやYANAPAKUNAでも活動を共にしたDante FloresとMarco Floresの兄弟もいた(インタビュー18分あたりではJosé Luis Manzaneda、Javier Valdiviesoという名前も挙がっているがメンバーだったかは不明)。とりわけEduardo Yañesを輩出したことは、このグループの隠れた功績だろう。
この曲をより世間に認知させたのはGrupo Andino de Oruroが1984年にカバーしたことによる(LAURO,BOLRL-1454,1984)。
 Grupo Andino de Oruro - COMO HAS HECHO
Grupo Andino de Oruro - COMO HAS HECHO
これ以降様々なグループがカバーして、南米全土に広がっていった。いくつか他のグループの演奏を紹介する。
 Grupo Amanecer Mi Saber
Grupo Amanecer Mi Saber
GRUPO AMANECER/DESTINO DE UNA MUJER A BOLIVIA(LAURO,BOLRL-1458,1984)。GRUPO ANDINO DE ORUROと同時期にリリースされたアルバム。Chuntunquiのリズムにアレンジしている。
 Dúo Hnos. Gaitán Castro - Como Has Hecho
Dúo Hnos. Gaitán Castro - Como Has Hecho
ペルーのGaitán Castroのカバーがこれまた大人気となる(Sunqumayu Producciones,1993)。以後このアレンジの演奏を多く聴くようになった。
 LOS TEKIS - Como Has Hecho
LOS TEKIS - Como Has Hecho
TEKISがこの曲をレパートリーに入れたのは1997年頃だろう。TEKISの定番曲となりアルゼンチンでも大ヒットする。
Hit Container '97
 Diosdado Gaitán Castro - Como Has Hecho(Nueva Versión)
Diosdado Gaitán Castro - Como Has Hecho(Nueva Versión)
ペルーのGaitán Castroが2022年に発表した新バージョン。他にも挙げればきりがないほどたくさんのグループが演奏している。コモ・ア・セチョの進化はまだまだ止まらないであろう。- 参考サイト
- YANAPAKUNA(ムシカ・アンディーナ・データベース内)
- ROMULO FLORES(ムシカ・アンディーナ・データベース内)
- Facebook(2023年2月10日Ishinoの書き込み)
(2024/9/24記)
- 参考サイト
- 夢想花 / 円広志
-
円広志の夢想花がスペイン語圏で流行した経緯を簡単に解説したい。
 夢想花(1978年) 円 広志
夢想花(1978年) 円 広志
この動画の解説欄に夢想花のヒットの経緯が書かれている。円広志はこの歌で『第16回ヤマハポピュラーソングコンテスト』および『第9回世界歌謡祭』(1978年11月12日)でグランプリを獲得。
この時、フランスのグループLOS MACHUCAMBOSが出場していて、URUBAMBA(Jorge Mirchbergの曲とは別)を演奏して入賞している。
翌1979年マチュカンボスはグランプリを獲得した夢想花をスペイン語に翻訳し「Donde Volabas」というタイトルでアルバムを録音する。翻訳したのはRafael GayosoとRomano Zanottiであると書かれている。ともにマチュカンボスのメンバーである(DIC談話室ロコト氏のご教示によるところが多い)。
 Los Machucambos - Donde Volabas
Los Machucambos - Donde Volabas
DISCOGS アルバムデータ SONOPRESSE 2s 008-16698 France 1979
https://www.discogs.com/ja/master/1648935-Los-Machucambos-Donde-Volabas-Caria-Elena
このアルバムは日本でも発売されている(RCA SS-3198)。
https://www.discogs.com/ja/release/28701298-Los-Machucambos-Donde-Volabas
1979年2月アルゼンチンタンゴの巨匠、オスヴァルド・プグリエーセ楽団に率いられてロス・ライカスが来日する。当時のメンバーは初期メンバーのカルロス・フローレスとホルヘ・スアレスと現在ロス・トレス・アミーゴスで活躍しているルイス・カルロス・セベリッチだった。そのコンサートでライカスは夢想花を演奏し、アルゼンチンに戻って、ブエノス・アイレスでこの曲をレコーディングした(ホルヘ・スアレス氏Youtubeコメント発言、現在その動画は削除されている)。
 Los Laikas DONDE VOLABAS
Los Laikas DONDE VOLABAS
DISCOGSデータ TONODISC DIF-1000 1979
https://www.discogs.com/ja/release/20367490-Los-Laikas-Donde-Volabas-Polvo-En-El-Viento
以前ルイス・カルロス・セベリッチ氏に会ったときに直接伺ったことだが、歌詞はマチュカンボスのスペイン語歌詞を踏襲したものの、前奏でケーナをいれたり、オリジナルのアレンジをすることで、南米ではマチュカンボスの演奏よりライカスの演奏のほうが普及したとのことだ。GRUPO ANDINOの演奏(Lauro,BOLCD-0041,1995)もロス・ライカスのものをベースとしている。その後もたくさんの南米のグループの間で演奏され続けている。
 GRUPO ANDINO ¿Dónde Volabas?
GRUPO ANDINO ¿Dónde Volabas?
(2024/10/10記)